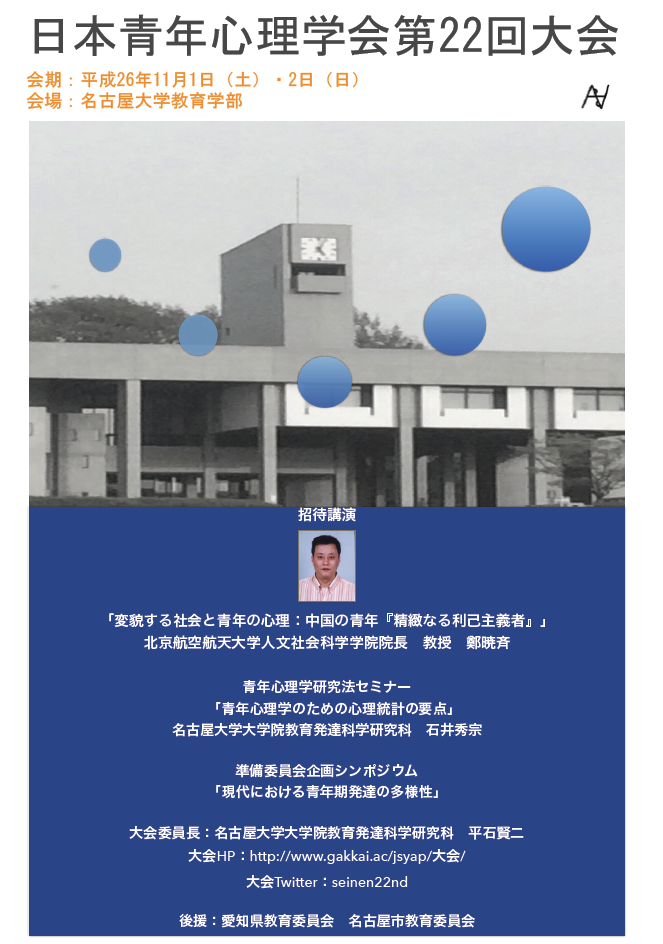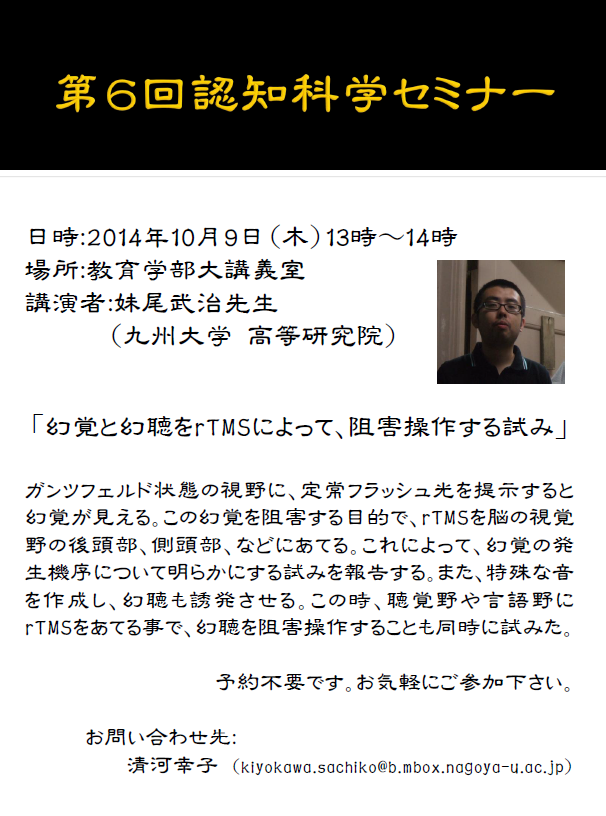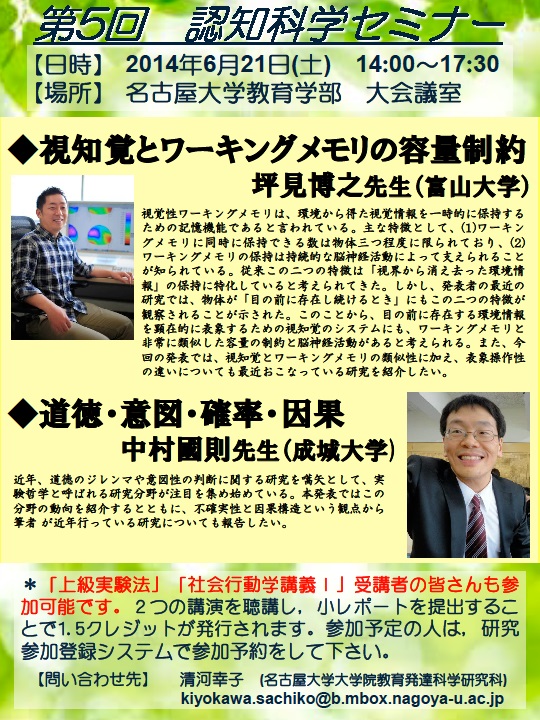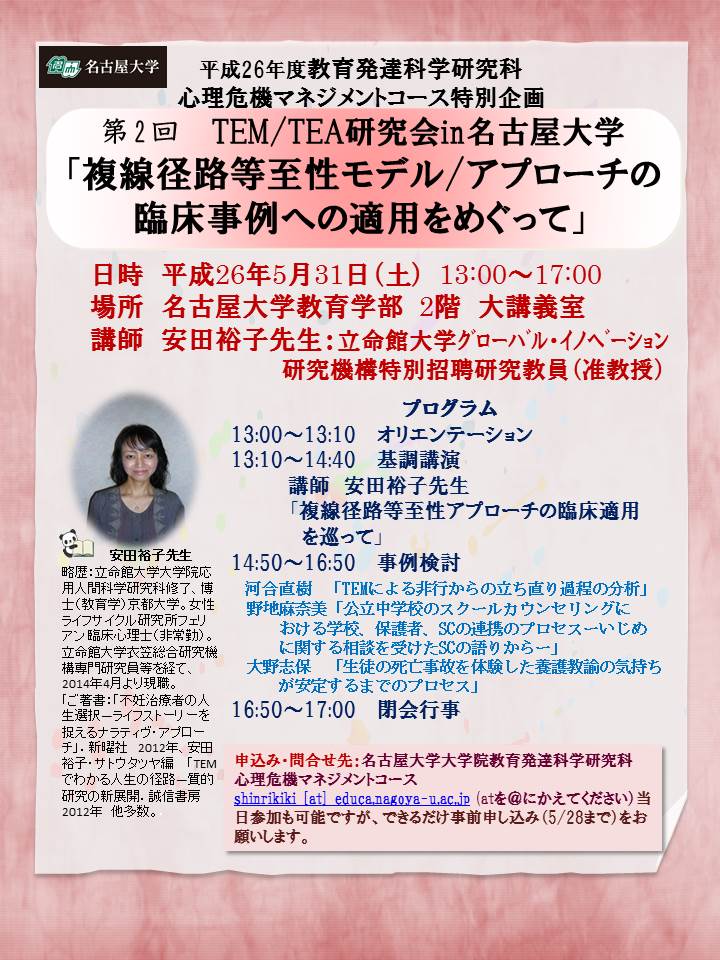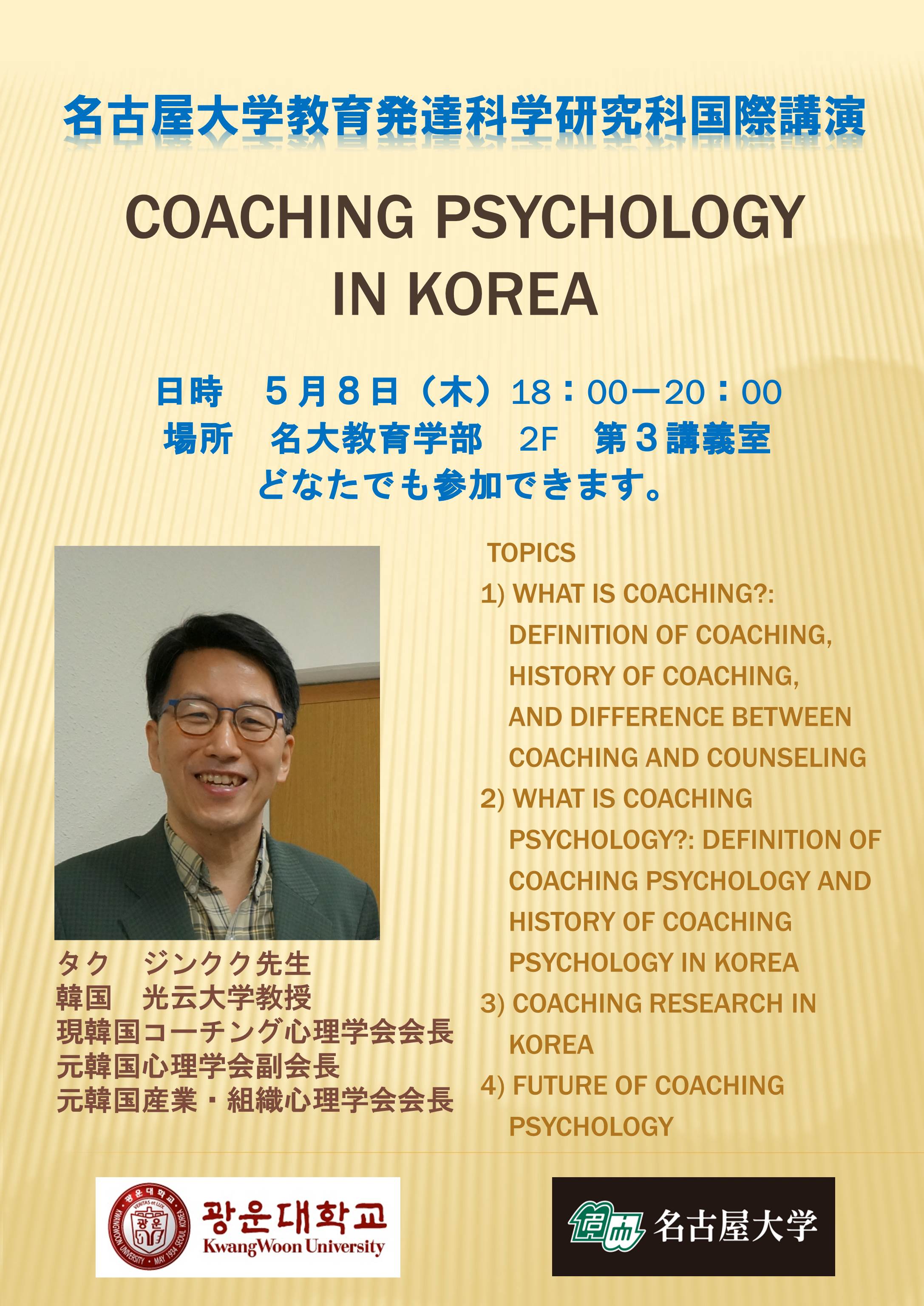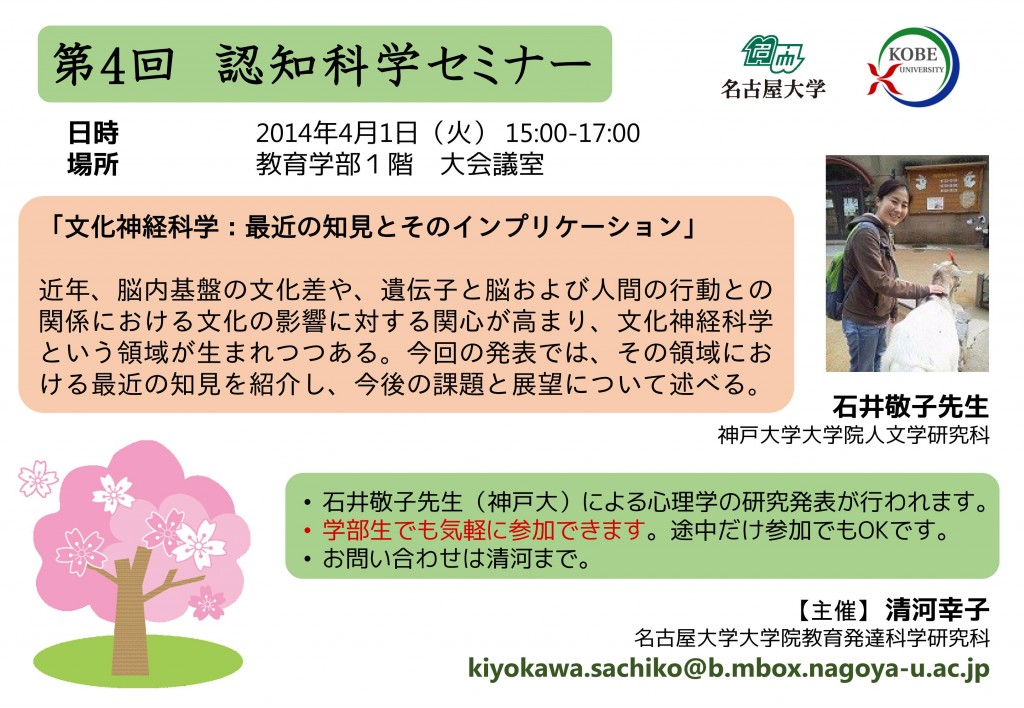2014年度第3回名古屋社会心理学研究会(NSP)を以下の通り開催します。発表者は愛知教育大学の黒川 雅幸氏です。
本研究会への参加は無料であり、どなたでも自由にご参加いただけます。また、事前連絡も必要ありません。多くの皆様のご参加をお待ちしています。
日時:2014年10月25日(土)15:00-17:00
場所:名古屋大学教育学部1F 大会議室
発表者:黒川 雅幸 氏 (愛知教育大学)
テーマ:もったいない感情に関する研究
概要:「もったいない」とは日本において長い間受け継がれてきた倹約の精神であり,モノが豊かではなかった時代においては,倫理として教育されてきた。モノが豊かな時代になっても,環境破壊を最小限に抑え,資源利用を持続的に行うために,今なお「もったいない」をスローガンに掲げた活動は様々なところで見られる。ところで,ある対象への金銭,時間,労力といった投資をし続けることが損失になると分かっていても,それまでの投資を惜しみ,投資をやめられないということがある(埋没効果:sunk cost effect)(Arkes & Blumer, 1985)。例えば,ダム建設や道路工事といった公共事業にも該当するケースはあるだろう。この経済的な不適応行動に影響しているのは「もったいない」と感じることであると考えられる。埋没効果は低次の動物や子どもには観察されない現象であると指摘されており(Arkes & Ayton, 1999),「もったいない」と感じることは比較的高次な活動であると推察できる。 本発表では,「もったいない」を認知的感情として捉え,感情としてもつ機能や,「もったいない」と感じやすい個人差,発達的変化に関する研究などについて報告したいと思う。
連絡先:名古屋社会心理学研究会事務局(担当:平島 socialpsychology758 [at] gmail.com)